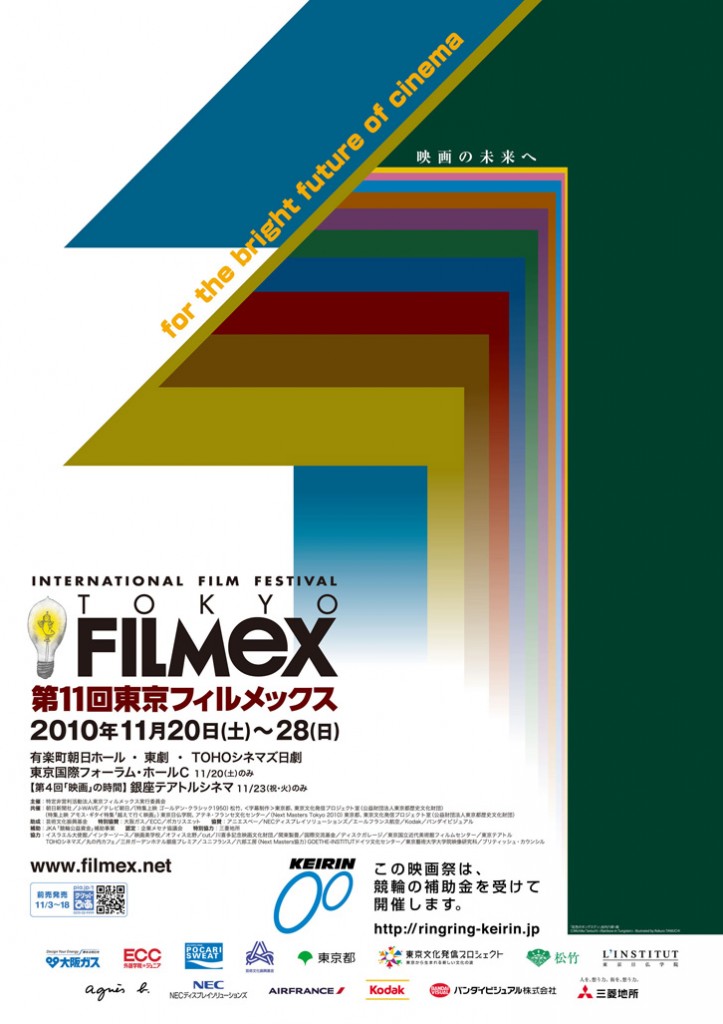第11回東京フィルメックスの特別招待作品として『溝』が上映された。
それは1950年代、異端分子として捉えられ強制労働キャンプに送られた人たちの、過酷を極める日常を綴ったドラマ。これまで『鉄西区』『鳳鳴―中国の記憶』などので賞賛を集めてきた中国人ドキュメンタリー作家ワン・ビン監督による初の劇映画だ。
もちろんワン・ビンの視点はこれまでの延長線上を見据えている。映画の質感は劇映画と言えどもドキュメンタリーに近い。音楽を用いず、ただ轟々と砂と嵐の饗宴が、鳴りやまないサントラのように絶えまなく耳を震わす。
日々、強制労働を耐え抜いては住居用の穴倉へと戻り、疲れ果てて寝床に倒れこむ。彼らが過去にどんな罪を犯したのかはそれほど重要ではない。また誰もが決して凶暴な人には見えない。彼らはまるで任意に抽出され、こんな地の果てまで連れてこられた酷く運に恵まれない人のようにも見える。それほどまでに彼らは人間性の長短や判断力も削げ落ち、過去も未来もなく、ただ茫然と生きている。
大自然の猛威に対して人間はあまりにも無力だ。収容された人々は極寒の中で食料も満足に貰えず、ある者は土や樹の芽をも口にし、そしてまたある者は正常であれば決して踏み越えることのない一線さえも越えてしまう。
同じ部屋の住人が死んだ。次第に哀しみもなくなる。それが日常となる。すべては砂漠に飲みこまれて、感情さえも枯れてしまう。観客もこの無力感の渦にどっぷりと漬け込まれ、もはや抵抗する気力や、ここから何か希望が実をつけそうな期待さえもとうに失っている。我々もあの穴ぐらの住人と化しているのだ。
と、そのとき、都会からひとりの囚人の妻が、遥々訪ねてくる。それほど美しくもないこの女性は、夫の死を知り堰を切ったようにワンワン泣きわめく。風の音しか聞こえなかったこの枯れ果てた風景を、うるさいくらいに掻き乱して、同居人たちを引きずりこむ。
囚人たちに取ってみれば迷惑な話だ。生き抜くために心をあえて無味乾燥せているというのに、そこに思わぬ“引き金”が舞い込んできてしまった。囚人たちの心と同調しつつあった観客ははた迷惑な女だと顔をしかめるかもしれない。
だが同時に観客はこうも気付くはずだ。ああ、この女性の姿こそが、当たり前の人間の姿だったんだ、と。愛する者に逢いたいと願い、泣きわめき、おびただしい墓の中から夫の遺体を掘り起こしたいとさえ望む彼女。
この映画『溝』で我々は見事なまでに人間性を見失い、そして彼女のやかましいまでの嗚咽によって再び人間性を回復させていく。これは我々の日常をリセットし、再起動させる意味において、とても不可思議かつ効果的な現象だった。
こんなにも絶望の物語なのに、不思議と後悔はなかった。単なる強制収容の逸話を越えた、獣でも悪魔でもない、真の意味での人間の物語に思えた。
その到達を讃えるかのように、ラストでは扉の向こうから僅かばかりの光が差し込んでいる。今も昔も、どんなに価値観が混濁して人々が人間性を見失おうとも、我々はあの光を手がかりに、暗闇の中を彷徨い歩いていけばよいのだろうか。ねえ、どうなんですか?ワン・ビン先生?
ワン・ビン監督は中国政府による圧力を恐れずによくぞこれほどの作品を作り上げたものだ。と、資料に目を通すと、製作国の欄に「フランス」とあった。今回のフィルメックスでは来日が叶わなかったそうだが、いつかこの映画について彼自身の口から多様な言葉が尽くされる日を待ちたい。
『溝』 The Ditch
フランス / 2010 / 109分
監督:ワン・ビン(WANG Bing / 王兵)
公式サイト http://filmex.net/2010/
【ライター】牛津厚信
カテゴリー: 東京フィルメックス特集 | 特 集
2010年12月2日 by p-movie.com